初心者のエレキギター選び【基礎知識】
『基礎知識講座』
『購入ガイド』
『練習と上達の知識』
『その他』
エレキギターとは?簡単な歴史と始まり
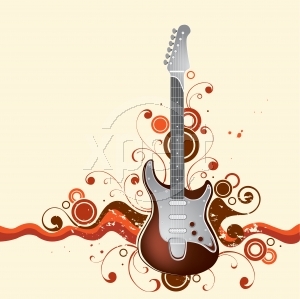
起源は一説によると1930年代にアコースティックギターにピックアップを取り付けたのが始まりで現在のエレキギターの原型のソリッドギターが発売されたのが1940年代と言われています。
1950年代に入るといよいよフェンダーのブロードキャスター(1951年発表後にテレキャスターと改名)が発表され大きく普及する事になります。
その後は現在でも人気のレスポール(1952年ギブソン)やストラトキャスター(1954年フェンダー)などが発表されてロックミュージックと共に人気になり数々の名モデルが生まれ現在に至ります。
他の伝統的な楽器に比べて比較的新しく歴史が浅いだけに、常識にとらわれない新しい奏法やサウンドが生まれる可能性を秘めている楽器と言えるしょう。
構造と材質
ほとんどのエレキギターのボディーの材質は木製で製造された上に塗装されて金属のパーツが埋め込まれています。
構造はアコースティックギターに比べてソリッド(薄く中身が詰まっている)つくりになっています。
弦は上から6弦(E)→5弦(A)→4弦(D)→3弦(G)→2弦(B)→1弦(E) となり(レギュラーチューニングの場合)1〜6の順番で弦が太くなっていきます。
主な特徴
従来のギターにPU(ピックアップ、マイク)を取り付けることによって弦の振動を電気信号に変えてアンプに出力する事で他の楽器にはないパワフルでサステインの効いた独自のサウンドを作り出す事が可能になりました。
このPUが複数付いているモデルは切換スイッチがあります。
これを切り替える事で音色が変化します。
エレキギターを普通にアンプに繋がずに弾いてもシャカシャカと鳴るだけで、CDやライブで聴くあの迫力ある音にはなりません。
エレキギター⇒シールド⇒ アンプと接続して初めてエレキギターとしての音が完成します。
スケールの違い
エレキギターにはスケールと呼ばれるネックの長さの基準があり各モデル毎に微妙に長さが異なります。
あまり極端な差はありませんがストラトキャスターに代表されるフェンダー系のギターはロングスケール、レスポールに代表されるギブソン系のギターはミディアムスケール、ムスタングに代表されるショートスケールがあります。
スケールが長くなるほどチューニングが安定して音にもハリが出ますが、テンションがきつくなり弾きこなすのにパワーが必要になります。
必要に応じてロングスケールの場合は弦をワンランク下げるとかショートスケールの場合は逆に上げたりして調整します。
また手が小さかったり指が短い人はフレットの間隔が短いショートスケールやミディアムスケールのモデルを考慮しても良いでしょう。
| ロングスケール(648mm) | ミディアムスケール(629mm) | ショートスケール(610mm) |
|---|---|---|
| ストラトキャスター、テレキャスターなど | レスポール 、 SGなど | ムスタング 、 ジャガーなど |
バンドでのエレキギターの役割
エレキギターは楽器パートの中でもリズムが主体のドラムやベースに比べて派手で目立ちます。
ですが通常のバンドの場合、やはり主役はヴォーカルです。
ギターは普段は伴奏をしていてサポートをしていますが、イントロやソロのここぞ!と言う時に目立って部分的に主役になれるパートです。
このメリハリこそギター最大の持ち味であり、バンドでの役割でもあります。
初心者のエレキギター選びトップ
よくある質問/
入門セット比較/
始めるのに必要な物は?/
用語集/
入門セット購入ナビ/
種類ボディータイプ別/